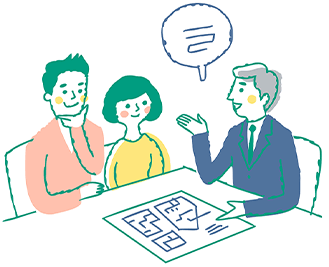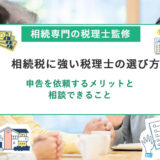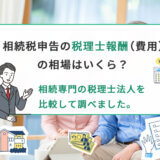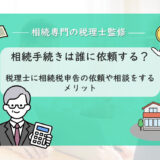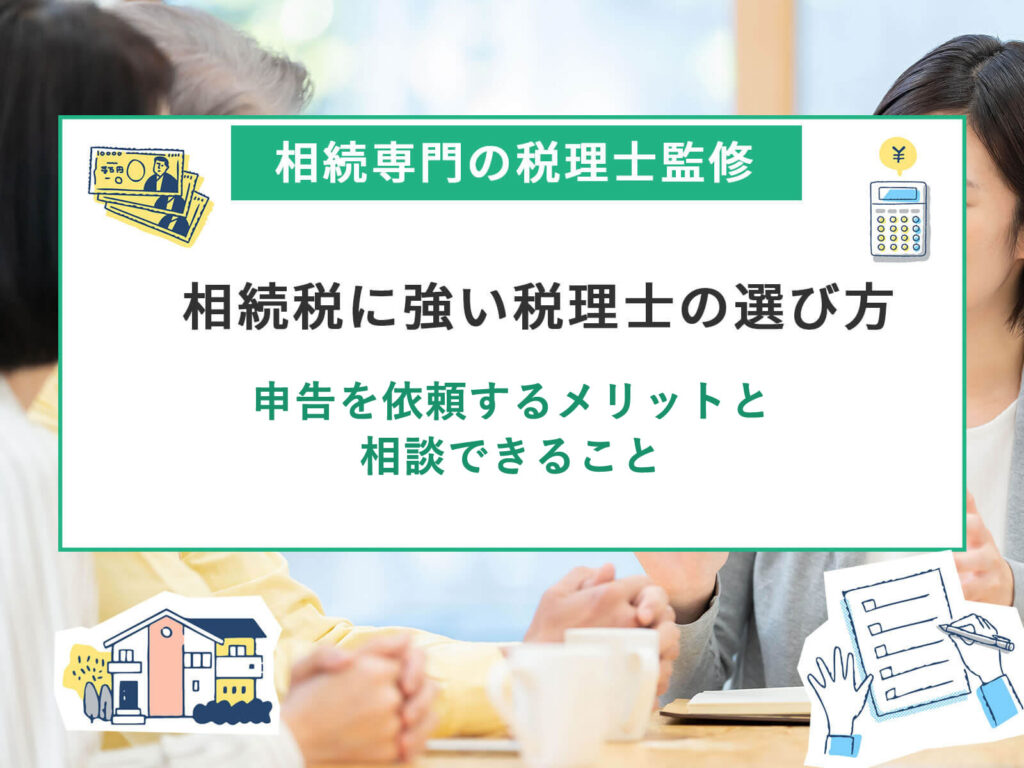
「相続税に強い税理士をどのように選べばよいのか分からない」
「相続の手続きをしたいが、何をすればよいのか分からないので専門家に相談したい」
「税理士選びで絶対に失敗したくない」
この記事では、そのような悩みを抱えている方に役立つ、「相続税に強い税理士の失敗しない選び方」を紹介します。
「相続税申告で必要以上に税金を払い過ぎた」「後から税務調査によって、罰則にあたる税金が課された」「担当の税理士の対応に不満がある」などの事態を回避することができます。
相続税申告が必要な方や相続税に強い税理士を探している方は、ぜひ参考にしてください。
この記事の監修/取材協力

古尾谷 裕昭 税理士
相続専門の税理士法人の代表税理士(VSG相続税理士法人)同事務所では、年間3,033件の相続税申告を行っており「99%税務調査が入ってこない」「税金を可能な限り安く」「親身に寄りそう」という方針で相続税申告を提供している。

近藤 洋司 税理士
相続専門の税理士法人、VSG相続税理士法人横浜オフィスの代表税理士。税理士になる前は不動産の仕事をしており「誰よりも不動産に詳しい税理士になる」という志のもと税理士になる。不動産の評価にとても強い。
税理士にもそれぞれ専門分野がある
税理士になるには、税理士試験に合格する、国税に勤務する(国税OB)、弁護士や公認会計士の資格を有するなどさまざまなルートがあります。税理士にはそれぞれ専門分野があり、得意とする税目は、税理士になるまでのルートだけでなく、どのような実務経験をしてきたかによっても異なります。
相続に強い税理士を選ぶポイント
ホームページなどで「相続税専門」「相続に強い」と明言している税理士はそれだけ相続税に自信があるといえます。ここでは、税理士を選ぶためのポイントを具体的にみていきましょう。
相続税を専門に扱っている事務所である
法人税や所得税の申告業務を主に行っている税理士事務所は、相続税申告をほとんど取り扱っていないことも多く、申告期限との兼ね合いなどからどうしても対応が後回しになり、申告期限ギリギリになることがあります。一方、相続税を専門に取り扱っている事務所であれば、相続税申告に特化しているため、申告までのスケージュールを意識して迅速に対応してくれます。
これまでの経験を活かし、申告書の作成だけでなく、不安を抱えている相続人の良きパートナーにもなってもらえます。
また、地方に住んでいる等の理由で、ご自宅の近くに相続税に強い税理士事務所がないという場合もあると思います。税理士事務所に通う回数は3回程度でかなり少ないです。さらに、大きな税理士事務所であれば、ZOOMや電話での全国対応可能なケースが多いため、そちらを検討してください。
年間の相続税申告の件数が多い
相続税を専門に取り扱っている事務所と、そうではない事務所では、年間の相続税申告の件数に大きな差があります。普通の税理士は年間に多くても1件程度です。相続専門の税理士事務所や税理士法人になると、1年間で少なくとも25件程度、多いところになると2000件以上の相続税申告をこなしているため、いろんな事例の経験やノウハウが蓄積されています。
司法書士など他の士業が在籍または提携している
相続財産に不動産が含まれていることは非常に多く、不動産を相続する場合には、名義変更の手続きが必要となります。この相続した不動産の名義変更の手続きを相続登記といい、税理士は不動産登記の手続きを行うことはできないため、司法書士など別の専門家に依頼することになります。
自分で司法書士を探す場合には、何を基準に選定するべきかなど悩むことも多いでしょう。一方、相続税専門の税理士に依頼する場合であれば、グループ内に在籍する登記申請に精通している司法書士や、提携している司法書士を紹介してもらえます。そのため、ワンストップで相続手続きを全て任せることができるため、依頼人としてはメリットが大きいです。
書面添付制度の利用実績がある
書面添付制度とは、税理士が申告書を税務署に提出する際に、申告書の作成にあたってどのような項目を確認し、検討したのかなどを具体的に記した書面を添付する制度です。
書面添付のメリットは書面添付をしていれば税務調査の対象になったとしても、税務署は納税者に直接調査に入ることができないことにあります。
「まず税理士にお伺いを立ててから」という流れになるため税務調査に発展する可能性も少なくなります。
書面添付制度の利用にあたっては虚偽の内容を記載すると、税理士業務の停止や税理士業務の禁止もあり得るため、申告内容に自信のない税理士は利用を避ける傾向にあります。相続税申告書に書面添付を行うことを明言している税理士であれば、相続税申告に自信があるといえます。
税理士が申告書を作成したとしても、この書面添付が必ずしもあるわけではないので注意しましょう。
料金体系を公表している
たとえ、遺産総額が同じ金額であっても、被相続人が所有する財産内容によって、税理士の作業工数は大きく異なります。
一般的に、作業量の違いを反映するために、相続税申告の料金体系は複雑になっていますが、複雑な請求額である理由をきちんと説明できる税理士は、料金体系をホームページなどで公表しています。
一生のうちに、相続税申告を経験する機会は1度か2度であるため、税理士報酬がいくらかかるのかは大きな不安材料になることでしょう。相続税の申告業務に重きを置いている税理士は、そのような相続人の気持ちも理解しているため、税理士報酬についての説明を避けることはしません。
相続税申告の税理士報酬の相場は遺産額の0.5~1%
平成14年までは、税理士会の税理士報酬規程によって報酬額が定められ、税理士が自由に報酬額を設定することは認められていませんでした。
この税理士報酬規程が廃止されて、税理士報酬が自由化された現在も、税理士報酬規程を踏襲して、遺産の総額の0.5~1%を税理士報酬額としている事務所が多いため、このような相場感になっています。
複数社、実際に面談してから決めること
インターネット経由で2~3社程度、このページを参考に税理士事務所を探して問い合わせてみて問題がなければ面談してみましょう。
そこで、分かりやすく説明してもらえるなど、寄り添った対応をしてもらえたかを確認します。
相続税理士マップのコールセンターでは、専門スタッフがご相談に乗っていますので、ぜひ一度ご連絡ください。
プライバシーにかかわる相談も多いため担当税理士との相性も大切
相続税に強い税理士を選ぶときは、税理士事務所の規模や代表の税理士だけでなく、窓口として実際にやり取りをすることになる担当者との相性も大切です。
どれだけ優秀な税理士であったとしても、相性が悪ければこれから大事な財産を守っていくパートナーとしてやっていくことにストレスを感じてしまうなど問題が出てきます。
また、相続税の申告書を作成するためには、被相続人だけでなく相続人の通帳なども精査する場合もあります。中には、被相続人に愛人や隠し子がいることが発覚するケースも少なくありません。
そのため、相続税申告を依頼するときは、このような込み入った話もできそうな担当者がよいでしょう。
主な業務が相続税申告ではない事務所の場合、相続税の申告書を作成できる担当者が1人しかおらず、担当者変更ができないこともあります。一方、相続税を専門とする税理士事務所であれば、担当者変更も可能です。
相続税の申告を専門の税理士に依頼するメリット
相続税専門の税理士に依頼すると、内容に誤りのない申告や、税務調査で指摘されにくい申告、申告期限を厳守した申告書の作成をしてもらえます。
相続税を抑えるための特例や税額控除、財産の評価方法に精通している
相続税は、被相続人が亡くなった時点で所有していた財産の評価額をもとに計算します。このときに、評価財産の減額要素や、適用できる特例や税額控除を見落とすと税額が高くなってしまいます。相続税専門の税理士であれば、適正な財産評価が可能です。土地など、遺産を安く評価できる部分は安く評価し、相続税を減額してもらえます。
個人で申告するよりも税務調査が入る可能性を抑えられる
相続税の申告書には税理士署名欄があり、この署名欄に税理士の署名があると、税務署は一定の知識がある人が作成した申告書であると認識します。そのため、無署名の申告書よりも評価方法や規定の適用誤り、添付書類の不足などがある可能性が低いという印象を税務署に与えることができます。また、税務署から問い合わせがあった場合、税理士が窓口になってくれます。
申告期限内に漏れのない申告書を作成してもらえる
相続税申告は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内に行わなくてはなりません。
しかし、相続が発生すると、相続税の申告だけに集中できるわけではなく、葬儀や役所での行政手続き、社会保険の手続き、水道光熱費の引き落し口座の変更など、やらなければならないことが山積みです。
そのような状況で、戸籍謄本や住民票、財産に関する資料などを収集し、相続人同士で遺産の分割方法を決めなくてはなりません。
このように、自分で申告書を作成するのは大変ですが、専門の税理士に申告を依頼すると、申告書の作成だけでなく、今すべきことなど申告書の作成以外のことでもサポートを受けられます。
相続について税理士に相談できること
税理士に依頼すると、相続税申告の作成はもちろん、相続について税理士に相談できることはたくさんあります。
相続税申告
相続税申告の代理業務を行えるのは、税理士や公認会計士*、弁護士*ですが、一般的に弁護士が相続税申告の代理を請け負うことはほとんどありません。
*税理士会に登録している弁護士や公認会計士の資格を有する者
相続税の申告書の作成を税理士に依頼すると、申告書を作成し、税務署への提出まで行なってくれるため、自分で提出する必要はありません。
申告以外の付随手続きも任せることができる
相続税の申告書には、戸籍謄本や原戸籍謄本、住民票など、さまざまな書類を添付する必要がありますが、これらの収集も税理士に依頼することができます。
相続税の試算
相続税は、一次相続において財産をどのように分割するかによって、二次相続での税負担が変わってきます。相続税専門の税理士に相談すると、二次相続まで考慮した相続税の試算をしてもらえ、どのように遺産分割を行うと税負担を抑えられるかのアドバイスを受けることができます。
生前の相続税対策
相続税に強い税理士に依頼すると、今後発生する可能性がある相続に備えて、どのような対策をすべきかのアドバイスをもらえます。
贈与
贈与は古くから相続税対策として行われており、認知度も高いですが、自己流で贈与するとかえって税負担が増えてしまうことがあります。贈与を検討している場合は、事前に税理士に相談することで相続税対策となる贈与の仕方を教えてもらうことができます。
遺言書作成
遺言書は自分で作成することもできますが、法的な要件を満たしていないと無効になってしまうこともあります。遺言書の作成を検討している場合は、税理士からアドバイスを受けることで、無効にならない遺言書を作成できます。
認知症対策
超高齢社会に伴い、認知症を患う人が増えています。認知症になると、生命保険の契約、贈与、金融機関からの借入など、法律行為ができなくなってしまいます。そのような事態に備え、認知症になる前に家族信託を契約することが重要です。税理士に依頼すると、家族信託の契約に向けてサポートを受けることができます。
税務調査の立ち会い
財産額が大きい場合、正しく申告書を作成して税務署に提出していても、税務調査の対象になることがあります。
税理士に依頼していると、税務調査となった場合に、どのようなことに気を付ければいいのかなど、事前にアドバイスを受けられ、税務調査の当日も税理士に立ち会ってもらえます。
まとめ
長年、相続税の申告に携わっている税理士は、相続の知識と経験が豊富で、相続税の申告をスムーズにこなすことができ、トラブルへの対処法も心得ています。
相続税に強い税理士を選ぶときは、「相続税専門の税理士」と明言していることに加え、年間の相続税申告の件数や書面添付の実施状況、相続関連の相談に対応してもらえるかどうかなどを確認した上で、相続税に詳しい税理士に依頼しましょう。

相続税に強い
税理士をご紹介します
- 身内が亡くなった、今すぐ相談したい
- 相続税申告について何も分からない
- 相続専門の税理士を紹介して欲しい
相続に関することであれば、どんなご相談でもお受けしています。
相談は無料です。繋がらないときはお時間をおいておかけ直しください。
私たちの想い
相続後に、
遺産をしっかり受け取り、安心して日々を過ごすことができるかどうか。
その鍵は、相続に強い税理士に出会えるかどうかが握っています。
例えば・・
- 申告に漏れがあれば、税務署から調査を受け追徴課税を支払う可能性がある
- 税理士が見つからず申告が間に合わなければ罰金を受けたり税金が高額になる
- 税理士が不親切であれば、よく分からないまま申告を行うことになる
など
実際に、
令和2年には、5,106件の税務調査が行われ、1件あたりなんと943万円の追徴課税が課されています。
相続に強い税理士がついていれば、まず税務調査に発展する可能性も低く、
追徴課税を受けるような抜けや漏れもないため、安心して相続税申告を終えることができます。
相続後の生活は、相続に強い、良い税理士に出会えるかどうかで決まるといっても過言ではないのです。
「亡くなられた方の遺産を、大事な方々にしっかりと残して欲しい」
「相続税のことで悩んだり、支払いに追われる様な方を1人でも多く減らしたい」
このサイトは、そんな想いで運営されています。