「登記事項証明書」完全まとめ|取得・記載方法・有効期限など迷わないための全知識
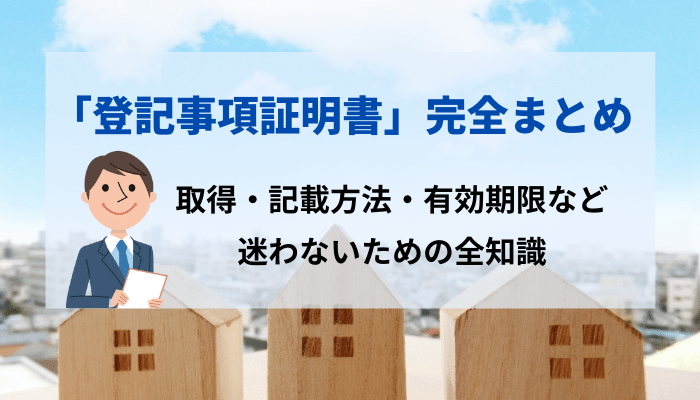
この記事でわかること
- 登記事項証明書の概念と種類
- 登記事項証明書の見方とチェックする際の注意点
- 登記事項証明書の取得方法
- 登記事項証明書の取得時の事前準備と注意点
- 登記事項証明書交付請求書の記入方法
目次
そもそも登記とは何か?
登記とは、法務局で登録されている土地や建物などの不動産の権利に関する情報のことです。
登録の対象となっている不動産について、誰がどのような権利を持っているかについての情報が記載されています。
権利については、不動産の所有者の情報だけでなく、住宅ローンを組む際に金融機関によって設定される抵当権などの情報も記載されます。
この情報には、現在の所有者や抵当権者だけでなく、過去の所有者や抵当権者などの情報も記載されています。
したがって、これまでその不動産が誰から誰にわたってきたのかを時系列的に追うこともできるのです。
不動産の売買の際には、この登記制度があるおかげで、対象となる不動産の所有権が自分にあることや売る権利を持っていることを証明できます。
不動産が売却されると不動産の名義変更がおこなわれます。
名義変更の際には、売主である元の所有者は自らの登記を抹消し、新たな所有者となる買主は自分の名前で登記します。
不動産を誰が所有しているのかを証明する登記においては、不動産を売買した際に登記の抹消と新たな登記、つまり名義変更を速やかに行わないと大きなリスクがあります。
というのも、真の所有者でない人が先に登記してしまったり、その人が次の買主に勝手に売却してしまったりする可能性があるからです。
例えば、Aさんが自分の不動産をBさんに売却し、その直後に今度はCさんにも同じ不動産を売却したとしましょう。
そしてCさんがBさんよりも先に登記を済ませてしまうと、Bさんは自分の所有権を主張できなくなってしまうのです。
不動産の速やかな名義変更は、不動産の売買時だけでなく、相続によって不動産を取得した場合にも重要です。
相続の権利を有する親族や身内などに、勝手にその不動産を売却されてしまう可能性もあるからです。
さらに、相続の状況によっては名義変更に予想以上の時間がかかる恐れもあります。
不動産の速やかな名義変更は、購入時だけでなく相続した場合でも重要です。
また、登記の情報は、不動産の買主にとっても、所有権のない人からの購入を避ける上で重要になってきます。
先ほどの例でいえば、Aさんから不動産を購入したBさんが、Cさんに先に登記されているにもかかわらず、そのことを知らずに自分の所有だと確信して、Dさんに売却する話を持ち掛けたとします。
しかし、Dさんは登記の内容を確認すれば、Bさんの名前はなくCさんの所有だということがわかり、所有権がないBさんから購入することは避けられます。
このように不動産の名義変更や登記の内容確認は不動産売買においてとても重要です。
なお、登記の申請自体は一般的に司法書士という登記の専門家に依頼しておこない、自分でやることはまずありません。
登記事項証明書とは?
まずは登記事項証明書の基本概念をご紹介します。
また、登記簿謄本との違い、さらに登記事項証明書の有効期限の有無についてもお伝えしていきます。
登記事項証明書の基本概念
登記とは法務局に登録されている不動産の情報で、登記事項証明書とは登記されている内容について証明する書類です。
法務局では登録されている不動産に関する情報は、コンピュータ内のデータベースで保管されています。
登記事項証明書は管理されている登記記録の電子データを専用の用紙で印刷したものです。
登記事項証明書に記載される情報は、対象となる不動産の所在地や面積などの物理的な情報や所有者の権利関係といった内容になります。
登記事項証明書と登記簿謄本の違いは?
登記事項証明書と登記簿謄本は名称こそ異なるものの、記載されている登記事項の内容は全く同じです。
それでは、なぜこのように名称が違うのでしょうか。
登記事項証明書が登場する前までは、登記事項の記録は全て紙媒体で管理されていました。
そのような登記に関する記録は「登記簿」と呼ばれており、紙媒体で管理されていたため「登記簿謄本」という名称がつけられていました。
平成元年(1989年)の商業登記法の改正以降、登記記録はコンピュータ内で電子データ化された上で管理されるようになり、登記事項証明書という名称に変わっていきました。
ただし、実際の不動産取引などでは、かつての呼び名で「登記簿謄本をご持参ください」などと依頼される場合もあります。
そのような場合は登記事項証明書の意味になりますので注意しましょう。
登記事項証明書の有効期限
公的な証明書では発行から3ヵ月以内などといった有効期限を定められていることが多いものですが、登記事項証明書に関してはそのような有効期限はありません。
あくまで登記情報が更新されておらず、最新の情報が記載されている証明書であれば有効になります。
したがって、不動産取引などで提出が必要になった場合でも、発行された日に関わらず利用することができます。
ただし、実際には「発行から○ヵ月以内に取得したものであること」といった条件が付けられる場合があります。
特に登記事項証明書が使われる住宅ローン申請時にはこのような有効期限が定められている場合が多いです。
したがって、登記事項証明書は必要な時に必要な分だけ取得するほうがムダを減らすことができるでしょう。
登記事項証明書の種類
| 種類 | 用途 |
|---|---|
| 全部事項証明書 | 現在事項証明書や一部事項証明書にする必要がある場合以外は、全部事項証明書を取得すればどのようなケースでも対応可能 |
| 現在事項証明書 | 現在において有効な登記事項のみ必要な場合 |
| 一部事項証明書 | 権利の一部について証明し、全部を証明する必要がない場合 |
| 閉鎖事項証明書 | 既に公開の対象から外されている過去の登記事項について調べる場合 |
| 共同担保目録 | 抵当権設定されている不動産を確認する場合 |
登記事項証明書は下記のように全部で4種類ある他、証明書にはなりませんが登記事項要約書もあります。
また、証明書の請求時にいっしょに取得できるものとして共同担保目録もあります。
使われるシーンによって取得すべき証明書や書類は異なってきますので、事前に用途を確認してから請求するようにしましょう。
登記事項証明書の種類
- ・全部事項証明書
- ・現在事項証明書
- ・一部事項証明書
- ・閉鎖事項証明書
- ・共同担保目録
全部事項証明書
全部事項証明書は、対象不動産について過去から現在にいたる全ての登記事項に関する情報が記載されている証明書です。
これには、所有者変更に伴う所有権の移転に関する情報、これまで設定や抹消されてきた抵当権の情報など、過去の全ての登記事項が記載されています。
後述する現在事項証明書や一部事項証明書にする必要がある場合以外は、全部事項証明書を取得すればどのようなケースでも対応可能です。
現在事項証明書
現在事項証明書は、今日現在において有効な登記事項のみが記載されている証明書です。
既に抹消されている過去の所有権や抵当権の情報は含まれていません。
現在事項証明書は、過去に差押えのあった不動産の場合、その事実を知られずに利用できます。
一部事項証明書
一部事項証明書は、「何区何番事項証明書」あるいは「登記簿抄本」などとも呼ばれ、不動産の一部の登記事項だけを証明する書類になります。
権利の一部について証明し、全部を証明する必要がない場合に利用されます。
例えば、区分ごとに所有者が異なるマンションの場合、全部事項証明書を取得すると全ての所有者の情報が記載されることになり、その量は膨大になってしまいがちです。
また、土地を複数の所有者間で共有しているような場合でも、その全ての所有者の所有権を証明する必要はありません。
したがって、証明が必要な部分だけを抜き出して証明することで煩雑さを回避したのが、一部事項証明書です。
閉鎖事項証明書
現在事項証明書が現在有効な登記事項だけを記載したものであるのとは対照的に閉鎖事項証明書では、既に閉鎖されている過去の登記事項のみが記載されています。
過去の登記事項とは、土地が「合筆」されて1筆の土地になり、建物が解体されて「滅失」したような場合にはそれらの登記事項については閉鎖されます。
登記簿に記載されている情報は誰でも閲覧可能なように公開されています。
しかし、既に公開の対象から外されている過去の登記事項について調べる場合は、閉鎖事項証明書を入手することでわかります。
ちなみに電子データ化される前の登記簿は、閉鎖登記簿または閉鎖謄本と呼ばれています。
共同担保目録
詳細は後述しますが、登記事項証明書を請求する際に請求書の「共同担保目録付」にチェックを入れると共同担保目録が入手できます。
登記事項要約書
登記事項要約書はメモに該当するもので、現在有効な登記事項のみが記載されます。
証明書ではないため、契約書などの添付資料として利用されています。
かつては登記簿しかなかったため、登記簿を閲覧した際にメモを取ることが許されていましたが、登記事項証明書はそのメモの代わりという位置づけです。
法務局が発行していますが、法務局の登記官の職印も発行年月日も記載されない簡易な書面になっています。
登記事項証明書を活用する場面とは?
登記事項証明書にはさまざまな用途があります。
どのような場合に必要になるかについてお伝えしていきましょう。
不動産購入時にローン申請する場合
マイホームなど不動産を購入する際には金融機関でローンを組むことが多いですが、その際に登記事項証明書の提出が求められます。
金融機関のほうでは、不動産の売買契約書上の内容と実際に登記されている該当不動産に関する情報の一致を確認するために請求されます。
不動産を売却または相続する場合
所有者以外の者が勝手に該当の不動産を売却していないかを確認するために、登記事項証明書で名義を確かめます。
また、相続の際には元の所有者であった被相続人と相続人との関係や相続関係そのものを証明するために取得します。
住宅ローン控除申請をする場合
住宅ローンがある場合は、一定の要件を満たしていればローン控除が受けられます。
ローン控除を受けるには、確定申告を済ませておく必要があります。
確定申告には申告用紙の他に必要書類を添付しなければならず、源泉徴収票やローンの年末残高等証明書などの他、土地と建物の登記事項証明書が必要です。
戸建て住宅の場合には全部事項証明書、マンションを購入した場合には一部事項証明書を取得の上で、確定申告用紙とともに税務署に提出することになります。
登記事項証明書の見方
登記事項証明書は主に「表題部」と「権利部」に分かれており、権利部はさらに「甲区欄」と「乙区欄」に分かれています。
表題部と権利部はそれぞれ、「表示登記」や「権利登記」と呼ばれることもあります。
表題部は不動産の所在などの状況を表わしたもので登記することは義務付けられていますが、権利部は一部を除き登記の義務はありません。
つまり、権利部には登記されていない事項が存在している場合がありますので注意が必要です。
それでは表題部と権利部にそれぞれどのような内容が記載されていて、どう見ればいいのかについてご紹介していきます。
表題部の見方
まずは土地を表示する場合の表題部についてですが、ここでは土地の「所在」「地番」「地目」「地積」「登記の日付」が記載されています。
地目とは、宅地や田畑など土地の使用目的のことであり、地積とは「~㎡」と表示される土地の面積を表わしています。
登記の日付は、二つの土地が一つになった合筆、それとは反対に一つの土地が二つに分割された分筆、さらに立ち退きなどで土地の交換がおこなわれた際の換地処分などが発生した日付のことです。
土地の所在や地番は住所と似ていますが、実際は全く異なります。
土地を調べる際に所在や地番がわからない場合がありますが、そのような時は法務局に問い合せるか、登記識別情報や権利証を見ればすぐにわかります。
一方で建物を表示する場合の表題部には、建物の所在や家屋番号の他、種類、構造、床面積、登記の日付が記載されています。
このうち、種類には「居宅」や「事務所」などの種別が記載され、構造は「木造瓦葺2階建」や「鉄骨鉄筋コンクリート造3階建」のように記載されます。
また、床面積は階層ごとの床面積が記載され、例えば「1階48.02㎡、2階32.50㎡」といった記載がされます。
また、マンションなどの区分建物の表題部は一般家屋とは異なる特徴があります。
それは表題部が、「一棟の建物の表示」「敷地権の目的である土地の表示」「専有部分の建物の表示」「敷地権の表示」と分けて表示されている点です。
証明書の冒頭にある「専有部分の家屋番号」とは、マンション内で所有者ごとに専有されている家屋のそれぞれの番号がすべて列挙されています。
例えば、「2-5-101」、「2-5-102」と各階の各号ごとの情報が記載されます。
以下に各表題部についてお伝えします。
表題部(一棟の建物の表示)
表題部(一棟の建物の表示)では、基本的に建物全体(マンションならマンション全体)に関する項目が表示されます。
ここでは調整・所在図番号・所在・建物の名称(マンションであれば「奥沢マンション」や「マンション八雲」といった名称)・種類・構造・床面積・登記の原因・登記年月日が記載されます。
所在については、例えば「世田谷区奥沢一丁目58番地1、58番地2」といった具合に表示されます。
この場合、マンションが複数の土地(上記の1と2)に跨って建っていることになります。
表題部(敷地権の目的である土地の表示)
また、土地が専有部分となる建物と一体化させるために敷地権とされている場合も、土地の符号・所在と地番・地目・地積・登記年月日の記載があります。
土地の符号とは敷地権の目的となる複数の土地を特定しやすくするために番号を付したものです。
表題部(専有部分の建物の表示)
表題部(専有部分の建物の表示)には、不動産番号・家屋番号・建物の名称・種類・構造・床面積・登記の原因・登記の年月日の記載があります。
このうち構造は鉄筋コンクリートなどと表示されています。
また、床面積は登記上の床面積のほうが、マンション販売の広告やパンフレットに記載のある床面積よりも小さくなっています。
これは、登記ではマンションの内壁線(壁の内側ということ)で算出されているのに対し、広告やパンフレットでは壁の中心となる壁芯で算出しているためです。
登記の年月日は新築年月日となっています。
表題部(敷地権の表示)
敷地権化されている土地の場合には表題部(敷地権の表示)として符号・敷地権の種類・敷地権の割合・原因とその日付が記載されます。
符号とは、複数の土地を特定するために土地ごとに符号1、符号2といった番号が付されており、その情報となります。
原因とその日付は土地が建物の専有部分と一体化された日の記載です。
権利部の甲区欄の見方
権利部の甲区欄には、土地や建物の所有者に関する事項が記載されています。
売買や相続などによって土地や建物の所有権が移転するたびに新たな枠で分けて、過去の所有者ごとに記載されていきます。
記載事項としては、順位番号、登記の目的、受付年月日、受付番号、原因、所有者となっています。
このうち、順位番号は登記された順番のことであり、登記の目的は所有権の保存や移転などの情報のことです。
原因には、その不動産の所有権が移転した理由(売買など)が記載され、所有者については住所と氏名が記載されます。
なお、権利部の甲区欄には「所有権移転仮登記」や「所有権移転請求権仮登記」といった登記事項の記載が見られる場合があります。
この所有権移転登記とは、土地や建物の売買予約契約を結んだ場合などに登記の順位を確保しておくために仮の登記をしておくことです。
購入対象となる不動産の売主が、所有権移転登記の手続きに必要な書類などを紛失しているような場合に、仮登記申請される場合が考えられます。
この仮登記で注意しなければならないのが、仮登記した権利者が本登記すると仮登記後に登記した所有者(最後の所有者)の所有権は登記官によって抹消されてしまうことです。
これは、仮登記権者が仮登記に基づいて本登記をすると第三者に対する対抗力が民法で認められているためです。
反対に仮登記しただけでは順位を確保する効力は生じていないということを意味しています。
そして本登記をしてはじめてその順位は仮登記の順位となり、仮登記後に登記した所有者に対してその権利が主張できる(つまり、第三者に対する対抗力)ことになるのです。
購入しようとしている不動産に仮登記がされているかどうかは登記事項証明書を見れば簡単にわかります。
仮登記されている物件は、上述のように所有権が認められなくなるリスクがありますので、不動産の購入前に仮登記の有無をチェックしておくことは大変重要です。
権利部の乙区欄の見方
権利部の乙区に記載される項目は、甲区の所有権以外の権利となります。
乙区の記載事項としては、抵当権や賃借権、地上権の設定や抹消に関する登記となります。
ここで記載される権利については、順位番号、登記の目的、受付年月日、受付番号、原因といった記載事項となり、それぞれの意味は甲区と同様になります。
ただし、乙区に抵当権が設定されている場合の記載事項には、ローンなどの債権額、利息、損害金、債務者、抵当権者が含まれています。
債権額は住宅ローンなどであれば銀行などからの借入額が該当し、利息や損害金は利率で○%という表示となります。
債務者は借りた人の住所や氏名が表示され、抵当権者は多くの場合、金融機関となります。
なお、甲区の所有権移転登記と乙区の抵当権設定登記の優先順位については、あくまで受付番号が早いかどうかで決まります。
これはそれぞれの登記が同じ日付でなされた場合であっても、あくまで受付番号が若いかどうかで優先順位が決定されることになります。
その他共同担保目録の見方
共同担保とは、複数の不動産に対して抵当権や根抵当権を設定することをいいます。
銀行などで住宅ローンを組んで戸建て住宅を購入するような場合、土地と建物の両方に抵当権が設定されます。
この場合、土地と建物の両方で共同担保となり、共同担保目録は担保設定の対象となっている不動産の一覧を記載したものとなります。
共同担保について確認するには、登記事項証明書の権利部の乙区とこの共同担保目録の両方を見ることになります。
権利部の乙区欄の「権利者その他の事項」の欄の最後に「共同担保目録第○○号」といった表記が見られます。
この表記に従って、該当する番号の共同担保目録を見れば、抵当権設定されている不動産にはどんなものがあるのかがわかるのです。
なお、共同担保目録は登記事項証明書の請求時に一緒に取得することができます。
登記事項証明書をチェックする際の注意点
登記事項証明書の基本的な見方がわかったところで、さらに重要なのがチェックする際の注意点です。
ここでしっかりと記載されている内容についてチェックしておけば、不動産取引を進める上でのリスクを未然に防いでくれます。
権利部記載の所有者と真の所有者の確認
まずは権利部に記載のある所有者が本当の所有者であるかどうかを確認する必要があります。
登記事項証明書の権利部に記載されている所有者は本当の所有者である場合がほとんどです。
しかし、中には諸事情により権利部の所有者が真の所有者でない場合がありますので注意が必要です。
通常の売買であれば、契約後の所有権移転の際に移転登記がおこなわれます。
しかし、相続や贈与によって持ち主が変わったような場合、この移転登記が行われないままになっているケースがあります。
また、中には相続が発生した際に相続人どうしで所有権の争いがおこっていて、移転登記にまで至っていないという場合も考えられます。
実は権利の登記は表題部の表示登記と異なり、義務とはなっていません。
そのため、権利部上の所有者と真の所有者が異なるといった事態が起こってしまいます。
抵当権の有無の確認
次に抵当権に関する記載の有無を確認するために権利部の乙区をチェックしてみてください。
抵当権が設定されている不動産の場合、権利部の乙区には抵当権の表示があります。
抵当権とは金融機関がローンなどの担保とするために該当の不動産に設定するものです。
もしローンの借主が返済できずそのローンが未回収となった場合、不動産を競売などにかけて処分し、未回収のローン債権に充当します。
抵当権が設定される不動産には、マイホームを購入したローンの借主が購入した不動産を金融機関の担保設定とする場合が一般的です。
その他にも他人のローン債務の保証人になった人が、自らの不動産に抵当権を設定する場合もあります。
もし、権利部の乙区に抵当権に関する金融機関名などの記載があり、その全てに下線が引かれていなければ、抵当権が設定されている不動産ということになります。
つまり、この不動産を購入するということは抵当権付きの不動産を購入することになります。
その場合、不動産の売買契約自体は有効ですが、ローン債権の未回収などが起これば抵当権者によって差押えられて競売にかけられるといった事態にもなりかねません。
抵当権者は抵当権設定後にその不動産を購入し、所有権移転のための変更登記を済ませていても、その所有者に優先してその不動産を処分する権利があります。
反対に抵当権に関する箇所に下線が引かれていれば、抵当権はすでに抹消されていることになります。
この場合、ローンは既に完済などがされていて抵当権の効力は既に失われているため、安心して取引を進めて大丈夫です。
権利部甲区上の差押登記の有無の確認
権利部の甲区に差押えの登記がないかどうかを確認します。
ここにその登記があれば、不動産が競売や公売の手続きに入った際に裁判所から差押えの登記がされます。
その場合、該当の不動産を落札した人に所有権が移転してしまいます。
登記事項証明書の請求と取得方法
登記事項証明書を申請するには、登記所または法務局証明センターの窓口での交付請求の他、申請書を郵送にて交付請求、オンラインでの交付請求の3つの方法があります。
また、受け取る際は申請した窓口か郵送になります。
取得方法や交付方法(受取場所)によって以下のように申請手数料が異なります。
| 請求書類 | 申請方法 | 交付方法(受取場所) | 申請手数料 |
|---|---|---|---|
| 登記事項証明書 | 登記所または法務局証明センターの窓口 | 登記所または法務局証明センターの窓口 | 600円 |
| 郵送 | 郵送※2 | 600円 | |
| オンライン申請※1 | 郵送 | 500円 | |
| (インターネット申請) | 登記所(または法務局証明センターの窓口 | 480円 | |
| 登記要約書 | 郵送 | 335円 |
※1オンライン請求ができない場合、最寄りの法務局窓口での請求のみとなります。
その場合、通常の窓口請求と同様、600円の手数料が発生します。
※2請求の際に返信用の郵便切手を貼付した返信用封筒を同封する必要があります。
法務局窓口で交付請求する方法
直接法務局の窓口まで出向き、窓口で申請してから取得する方法です。
法務局の他、支局や出張所でも取得可能ですので、自宅そばの最寄りの施設を探してみましょう。
窓口で入手できる登記事項証明書交付請求書に必要事項を記入の上で提出すれば受け取ることができます。
もし、あらかじめ準備しておきたいのであれば、法務局のホームページから請求書をダウンロードし、印刷した請求書に記入しておくことができます。
申請手数料は窓口交付の場合、600円の収入印紙を購入し申請書に貼り付けて提出します。
郵送で交付請求する方法
法務局や支局などの窓口か、法務省の「登記・供託オンライン申請システム」からダウンロードして登記事項証明書交付請求書を入手し、必要事項を記入の上で郵送にて交付請求します。
また、受け取りについても郵送で対応してもらえます。
なお、交付請求書を郵送で送って請求する際、返信用の郵便切手を貼付した返信用封筒を同封する必要がありますので、忘れないように注意しましょう。
郵送での交付請求の場合、申請手数料は600円となります。
手数料の支払いは、ネットバンクやペイジー、モバイルバンキング、電子納付対応のATMから可能です。
なお、支払期限は、上記の「登記・供託オンライン申請システム」で必要事項を入力後に表示される「かんたん証明書請求」や「申請用総合ソフトの処理状況画面」で、金額が表示されてから1日以内となりますので、速やかに支払いを済ませる必要があります。
オンライン上で取得する方法
インターネット上で法務省の登記・供託オンライン申請システムにアクセスし、必要事項をすべてオンライン上で入力して交付請求する方法です。
受け取りについては郵送と窓口から選ぶことができます。
急ぎで入手する必要がある場合は、窓口まで取りに出かけたほうが郵送よりも早いかもしれません。
申請手数料は窓口にて受け取る場合は480円、郵送による場合は郵送費用込で500円です。
登記要約書の交付請求方法
登記要約書は既にご紹介したように証明書ではありません。
取得方法ですが、まずはインターネット上の「インターネット登記情報提供サービス」にアクセスします。
自分の個人情報を登録の上でログインし、必要な情報を入力すると登記情報要約書を取得できます。
手数料は1通あたり335円が発生します。
登記事項証明書の取得時の注意点とは?
登記事項証明書を取得する際には、なるべくスムーズに手続きを済ませられるように以下にお伝えする注意点に気をつけましょう。
受付窓口の最新情報をチェック
登記所や法務局、支局、出張所の窓口で申請す場合は、事前に訪問する施設の最新情報をチェックしておくといいでしょう。
登記簿の情報が電子データ化されるとともにオンライン申請が増えてきているため、局や出張所の統廃合が進んでいます。
もし、申請しようと法務局に向かったものの、閉鎖していたということになればムダになってしまいます。
訪問する前にあらかじめインターネットで確認するか、電話で問い合わせてみましょう。
受付時間の確認
法務局の窓口で交付請求する場合の受付時間を確認しておきましょう。
受付時間は平日午前8時30分から午後5時15分までとなっており、土日祝日や年末年始(12月29日~1月3日)は受付していません。
受付時間内であれば、昼休みはないために常時受け付けてくれます。
なお、法務局のコンピューターは午後5時15分をすぎるとすぐに閉じられてしまいますので、時間に余裕をもって受付終了時間よりも少し早く到着するようにしましょう。
申請件数が非常に多くて処理に多大な時間がかかるような場合は、業務時間内に請求しても交付が翌日になってしまうこともあります。
また、インターネットからオンライン請求した場合も、受付時間は平日の午前8時30分から午後9時までとなっています。
午後9時以降の請求は、窓口で請求する場合と同様に翌日の取扱いになります。
データ化されていない登記記録や関連情報に注意
登記簿はかなりデータ化が進んではいるものの、全てがそうなっている訳ではありません。
地積測量図や公図、建物図面などはまだ一部でデータ化が進んでいないものもあります。
データ化されていない登記簿の記録についてはオンライン請求ができませんので、管轄している法務局や支局、出張所に出向く必要があります。
この場合、管轄外の法務局では取得できない場合も多く、管轄の登記所に該当するかどうかは登記の区分で異なってきます。
不動産登記については、不動産登記管轄区域内で該当の管轄登記所を事前に確かめておいたほうがいいでしょう。
いずれにしても、データ化されていない記録については事前に法務局に確認の連絡をしたほうがスムーズです。
管轄法務局かどうかを調べる方法
対象となる不動産の管轄法務局であるかを事前に調べるには、2つの方法があります。
まず、法務局のホームページにアクセスし、「管轄のご案内」のページに進みます。
同ページには全国の登記所の住所や電話番号、不動産登記管轄区域と商業・法人登記管轄区域ごとの法務局や支局、出張所の情報が掲載されています。
各局の地図や交通手段についての情報もありますので、事前にチェックできます。
管轄法務局かどうかについては、電話による確認も可能です。
確認する場合、対象となる不動産の最寄りの登記所や自分が住んでいる都道府県にある登記所である必要はありません。
なお、法務局は北海道以外では各都道府県に1拠点ずつしかありませんので、覚えておくといいでしょう。
登記事項証明書の請求前に準備しておくことは?
登記事項証明書の請求に必要なものをご紹介します。
一回の請求でスムーズに済ませられるように、しっかりと準備してから出かけましょう。
地番や家屋番号等の正確な情報を入手
登記事項証明書の請求する際は、まずは対象となる土地や家屋などを特定するための「地番」や「家屋番号」を調べておきます。
地番というと私たちが普段使用している住所とほぼ同義となる住居表示を思い浮かべるかもしれませんが、請求に必要な地番は住居表示とは異なります。
ただし、市町村によっては、住居表示に関する法律制定前のように地番のみで管理しており、未だに住居表示と地番が同じ地域もあります。
また、家屋番号は建物を特定するための番号のことで、特にマンションなどの集合住宅に関連する情報です。
地番や家屋番号を調べる方法については次にご紹介します。
地番や家屋番号を調べる方法
まず家屋番号については、管轄の都道府県の法務局窓口で尋ねるか、電話で問い合わせることで調べることができます。
その際には、対象の建物の「名称」「地番」「部屋番号」の3点を聞かれるので、事前に確認しておきましょう。
また、地番の調べ方については以下のようにいくつかの方法があります。
法務局
家屋番号と同様に管轄の都道府県にある法務局窓口に直接訪問して尋ねるか、電話で問い合わせることができます。
その際には、調べたい対象の不動産の住所を伝える必要があります。
ブルーマップ
ブルーマップとは、地図の上に公図を重ねた地図のことです。
最寄りの法務局の他、大きな図書館や市役所でも閲覧できます。
ただし、無料なのは法務局のみです。
法務局を訪問する場合、職員に直接尋ねてみてもいいでしょう。
地番検索サービス(インターネットによるオンラインサービス)
インターネット環境さえあれば、登記要約書の交付請求方法でご説明した「インターネット登記情報提供サービス」のホームページにアクセスすることで、自宅にいながらでも調べることが可能です。
ただし、インターネット検索のシステムは全ての情報を網羅していないことも多く、限界があります。
もしシステムを利用してもわからない場合は、直接電話等で法務局に確認する必要があります。
インターネット登記情報提供サービスの利用方法は、同サービスのページにアクセス後に「一時利用」をクリックし、必要な情報を入力します。
利用規約に同意の上、氏名(仮名含む)・パスワード・電話番号・Eメールアドレスを入力すると、登録したEメールアドレスに「ログインID」と「ログインパスワード」が送られてきます。
ログインしたら、画面上にある「不動産請求」をクリックし、さらに「地番検索サービス」もクリックします。
左側の欄に調べたい都道府県が検索できますので、対象の住所をクリックすると番地と地図を見ることができます。
なお、この検索サービスはブルーマップの情報を基に作成されているため、ブルーマップに掲載のない地番については調べることができません。
市役所・企業局
職員に該当の不動産の住所を伝えて調べてもらうことができます。
ブルーマップで調べるように指示された場合は、有料になりますが同マップにて自分で調べることになります。
公図
有料ですが公図を取得すれば、ブルーマップにはない、より詳細な地番の情報を入手することができます。
例えば、公図を利用して隣接地との正確な境界線の位置がわかるようになります。
新たに土地を購入したものの、公図と現況が大きくずれているような場合や、隣の家との境界線が曖昧な場合、将来トラブルの原因になりかねません。
そのようなケースでは、公図で正確な隣接地に対する位置関係を確認しておくことで、トラブルにならずに済みます。
公図は法務局または「インターネット登記情報提供サービス」のホームページから入手することができます。
公図を請求する際は、申請書の提出が必要となります。
申請書には申請者の住所・氏名・対象となる不動産の所在地を記入の上、証明書か閲覧を選択し、図面の種類を選びます。
閲覧を選ぶと見るだけになっていますので、「証明書」を選択しましょう。
なお、申請書は必要事項を記載して提出すればすぐにその場で公図を取得することができます。
登記事項証明書交付請求書の用意
登記事項証明書の交付請求をするには、請求書を入手し提出する必要があります。
法務局の窓口で直接申請する場合は法務局内で入手できますので、当日出かけた際にその場で必要事項を記入して提出可能です。
窓口で請求書を提出すると番号札が渡され、呼ばれると必要な情報を開示してくれます。
その後、証明書が発行され交付となります。
なお、事前に請求書を用意しておきたい場合は、窓口で入手しておくか法務局のホームページからダウンロードすることもできます。
手数料の用意
証明書の請求には手数料が必要です。
詳細についてはすでにご紹介した一覧をご覧ください。
なお、手数料については窓口での請求よりもオンライン上での請求のほうが安く済みます。
また、50枚以上請求する場合、50枚目以降については50枚ごとに1枚あたり100円の手数料が発生しますので注意しましょう。
登記事項証明書交付請求書の記入方法
登記事項証明書交付請求書を記入する前にまず入手した請求書が「不動産用」と記載されたものかどうかを確認してください。
不動産用の請求書であれば、次に太枠の中の各項目を記入していきます。
住所・氏名
ここでは申請者の住所を記入し、会社(法人)であれば会社の住所を記入します。
次に氏名を記入しますが、フリガナの記入も忘れないようにしましょう。
間違って平仮名を記入しないように気をつけましょう。
種別から請求通数まで
ここでは対象の不動産について記入していきます。
種別は土地か建物のいずれかを選んで「レ印」でチェックします。
注意が必要なのは、地番と家屋番号の記入です。
地番と家屋番号は、すでにご説明したように普段つかっている住所(住居表示番号のこと)とは異なりますので間違えないようにしましょう。
先ほど請求前に事前に調べておいた情報をここに記入します。
請求通数とは必要な枚数分になります。
請求書類の種類
請求書は全部で5種類あることをご紹介しましたが、ここでは請求対象となる書類の□のところに「レ印」をつけます。
最も請求することの多い登記事項証明書・謄本については、現在効力のある登記事項のみにするのか、あるいは過去に抹消された登記事項を含む全ての事項の記載とするのかについて選択できるようになっています。
現行で有効な登記事項のみが記載されている証明書を入手したい場合は、「ただし、現に効力を有する部分のみ(抹消された抵当権などを省略)」という箇所に「レ印」を入れてください。
一部事項証明書と所有者事項証明書については、共有者がいる場合にその情報が必要になります。
共有者の正確な住所・氏名・持分の情報は事前に入手しておきましょう。
また、合筆・滅失などに伴う閉鎖登記簿・記録については閉鎖された年月日を記入することも忘れないようにします。
収入印紙
手数料については、収入印紙を窓口で購入しておきます。
購入した収入印紙は請求書の右側の欄に貼り付けて提出してください。
なお、記入する欄はあくまで太枠の中のみとなります。
一番下の欄は法務局の職員が記入する欄ですので、誤って記入しないように気をつけましょう。
まとめ
登記事項証明書についてその基本概念から取得の方法までをご紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。
あまり聞きなれない言葉も多くて、少し戸惑ったかもしれません。
さまざまな専門用語が出てきますが、基本的にはそれぞれの対象となる不動産の履歴書に相当するのが登記簿であり、登記事項証明書となります。
実際の不動産取引では司法書士に取得を依頼することがほとんどですので、その全てを知る必要はありません。
ただし、今回ご紹介した範囲の内容はマイホームの購入時など不動産取引において大切なポイントをたくさんご紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。
